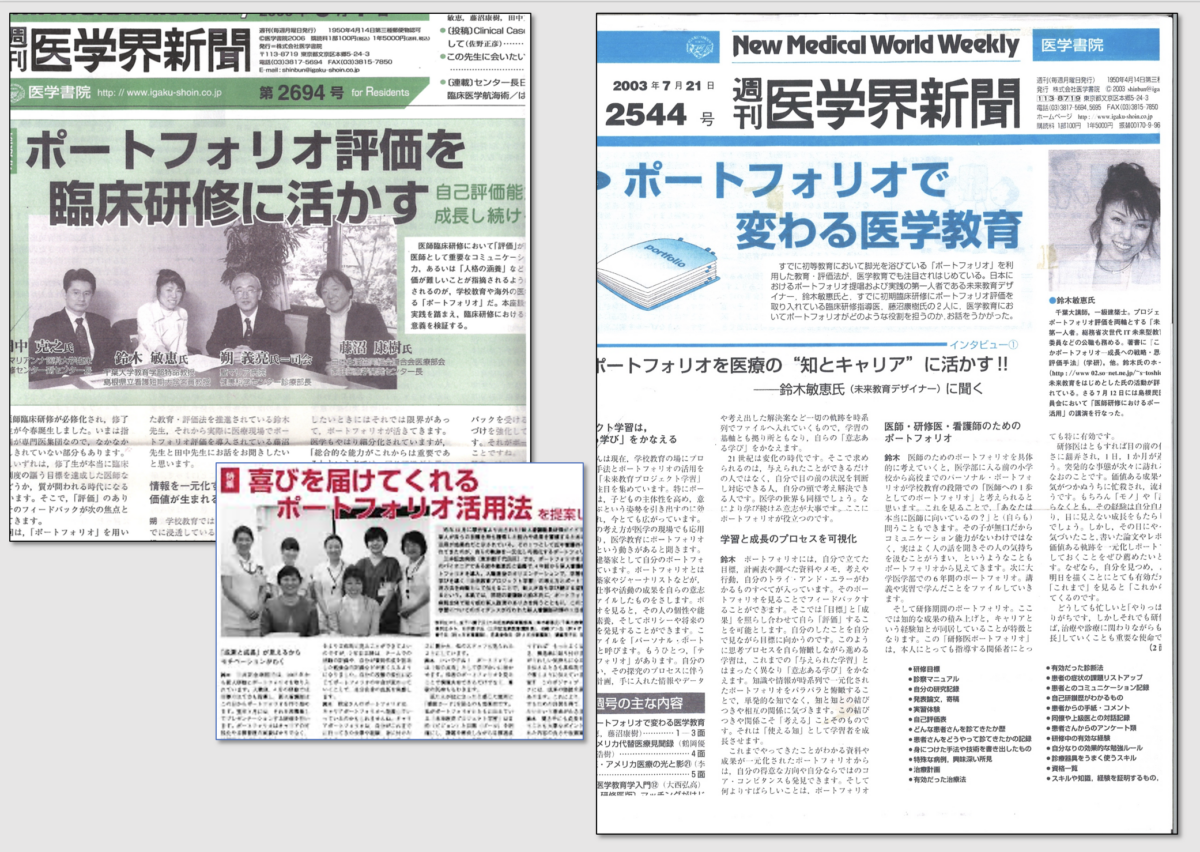AI時代の看護教育(インタビュー)—「意志ある学び」を実現するために(医学界新聞)
2025年6月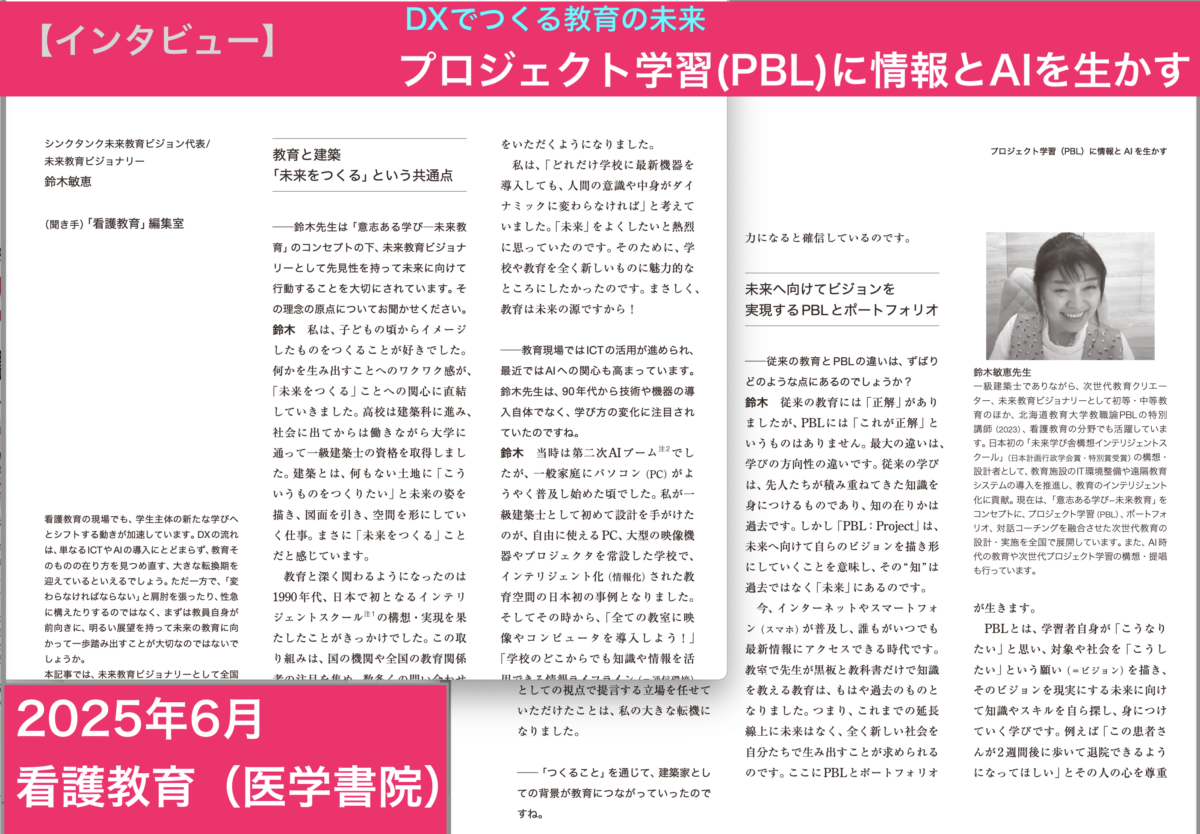
2017年4月
-1.png)
AI時代の看護教育
「意志ある学び」を実現するために
●すずき・としえ氏
シンクタンク未来教育ビジョン代表。教育クリエーター、一級建築士。日赤秋田看護大学大学院非常勤講師。教育界、医学界など高度専門領域におけるアドバイザーとして、プロジェクト手法やポートフォリオ評価、次世代教育構想コンサルタントも行う。大学FD構築、新人研修、指導者育成、キャリアデザインを目的とする人材育成などを全国で実施。「看護師の実践力と課題解決力を実現する! ―ポートフォリオとプロジェクト学習」「アクティブラーニングをこえた看護教育を実現する ―与えられた学びから意志ある学びへ」(いずれも医学書院)など著書多数。
interview 鈴木 敏恵氏(シンクタンク未来教育ビジョン 代表)に聞く
「AIに奪われる仕事」が話題になる中、教育の分野は「知識を与えるだけの教育」から「知識を与えない教育」へと転換している。看護教育もアクティブラーニングをはじめ、能動的な学習方法が積極的に取り入れられつつある。その学びを実践でさらに生かすために、看護は何をどのように教えればよいのだろうか。本紙では、オリジナリティあふれる教育手法を長年発信し続ける鈴木敏恵氏に、自ら学ぶ力を身につけるための教育と、これからの看護教育がめざすべきビジョンについて聞いた。
──先生はこれまで、看護教育へのアクティブラーニング導入など、従来の教育手法からの転換を訴えてきました。どのような背景があるのでしょう。
鈴木 AI(人工知能)時代が到来しようとしている今、正解が決まっているもの、意味がわからなくてもできてしまう仕事はAIに取って代わられてしまいます。AIが持ち得ない能力を高めるために、学習者に一方的に知識を教えるだけの教育から、学習者主体の学びへと転換する必要があります。
──高度な認知能力によって状況判断できるAIの登場で、看護の現場はどのような変化が起こると予想しますか。
鈴木 例えば、病棟のさまざまなモノがIoT化され、看護師が観察する情報がAIネットワークと結ばれれば、患者がベッドに寝ている間のバイタルサインを含めあらゆる情報をアセスメントできるようになります。寝返りを打てなかった昨日までは違う何らかの兆候や危険因子も、画像認識によるアラーム機能で知らせてくれるでしょう。
将来的には、AIが測定データと電子カルテ情報を複合して基本的な看護計画や治療方針の策定、さらには退院後、地域の社会資源活用のプランを提示するなど、仕事内容が劇的に変わることは間違いありません。
重視すべきは「センシング力」と「課題解決力」
──では、AI時代に身につけるべき能力はどのようなものでしょうか。
鈴木 次世代教育に求められる修得知として私が提言してきたA〜Dの4つの領域です(図1)。Aの「知識やスキル」が大切であることは間違いありませんが、これはAIが得意とするところで、社会の進化とあっという間に陳腐化する可能性があります。一方で、何が起こるかわからない現実世界の不確実性には、AIは弱いんです。
そこで、Cの「コンピテンシー」、Bの「知性・精神」、Dの「ビジョン力」を身につけることが切実です。特にこれからの未来を描く力であるDが重要です。ありたい像(ビジョン)があることで現実とのギャップに気付き、課題解決力が身につきます。
●図1 未来教育──4つの修得知モデル
(『アクティブラーニングをこえた看護教育を実現する』より)
──指導者が教えるに当たり、意識すべき点はありますか。
鈴木 「人間にしかできないことは何か」、「教育で何を提供すればよいか」の二つを考えることです。前者はDの「ビジョン力」です。AIは、人間のように自ら未来を描くことはしません。看護師は、患者さんへの励ましや優しさを、言葉やタッチングの手のひらで伝え、退院後の患者さんが「こうあったらいいな」とQOLを尊重しながらビジョンとゴールを描けます。
後者は、「課題発見、解決力」に必須の「センシング力」です。総務省は2016年、日米の就労者が考える「AIの活用が一般化する時代における重要な能力」を調査しました(図2)。米国の就労者は「情報収集能力」「課題解決能力」を特に意識しています。業務の完遂を第一に求められる米国ならではの事情が反映されていますが、看護師の「資質」とも重なります。
──AIが活用される中、人間にさらに求められる能力と言えそうです。
鈴木 はい。センシングで目の前の状況を把握することができなければ、どんな能力やスキルも発揮することはできません。学生や新人看護師に知識があっても、現場で力を発揮できないとの声をしばしば耳にします。教育現場にセンシング力を教える場面が少ないため、若者も身につけていない傾向があります。机上のシミュレーションやインシデント学内演習ではなく、現実の場でしか修得できない力なのです。
意志ある学びをかなえるビジョンの力
──先生は「アクティブラーニングをこえた教育」を提言しています。具体的な内容を教えてください。
鈴木 アクティブラーニングは手段であって目的ではありません。めざすのは、その先の「アクティブ・シンキング」です。アクティブとは「主体的」の他に「敏活」の意味もあります。アクティブになるためには「何のために」「何をやり遂げたいのか」という目的と目標が必要です。主体的とは単に「自分から動く」のではなく、センシング力を発揮して目の前の課題を発見し、情報を獲得して解決へと向かうことです。
その過程で得た情報や、思考、判断を客観的に見る「メタ認知」によって自覚的に成長することができます。その有効な手法が「次世代プロジェクト学習(Project Based Learning)」(以下、プロジェクト学習)という、ポートフォリオ、計画、コーチングを融合させて私が構想したものです。
「未来がこうだったらいいな」と思うことってありますよね。その「ありたい姿」を学習者が描ければ、自身の課題に気付き、解決や実現に向けて進んでいくことができるのです。
──「意志ある学び」を理念とする、プロジェクト学習の広がりが期待されますね。
鈴木 そうですね。取り入れることで、学生のモチベーションがぐっと上がります。導入校からは、「看護師国家試験の結果が飛躍的に向上しました」と、この4月もうれしい知らせが届いています。
学生が「看護師になりたい!」というビジョンを強く胸に持ったからだと、先生方が教えてくれました。
──より高度なアクティブラーニングと言えるプロジェクト学習を、教員は、どこから始めればよいでしょう。
鈴木 学習者がビジョンとゴールを考えるところからです。プロジェクト学習の出発点となる「ゴールシート」(注)を用い、めざすゴールを記入したら、ポートフォリオの1ページ目に入れます。リフレクションとリフレーミングの「2つのR」も大切です。振り返るだけでなく、違った見方をすることで発想が広がっていく。その思考過程がポートフォリオで見えますから、課題発見から解決に至る一連のプロセスが明らかになります。「患者さんによくなってほしい」、そのビジョンを胸に学び続ける人に育ってほしいですね。
──技術革新が進む時代、看護教育が進むべき新しい方向性とは。
鈴木 はい。AI時代の将来、自ら課題を発見し、解決に向かおうとする看護師は、ますます求められます。
この世界は「知の果樹園」です。リンゴに気付ける人、取りたいと思っている人にとっては、その環境が無限に広がっている。研修や授業だけが学ぶ場ではありません。与えられた学びから意志ある学びへと自分で成長させられる人を育てる。それが、私たちのめざす教育のゴールだと信じています。(了)
●参考文献
1)総務省.ICTの進化が雇用と働き方に及ぼす影響に関する調査研究.2016.
医学界新聞 〔特集〕ポートフォリオで変わる医学教育(インタビュー)
初等教育で脚光を浴びる「ポートフォリオ」を医学教育に導入する意義について、日本におけるポートフォリオ提唱および実践の第一人者である未来教育デザイナー・鈴木敏恵と臨床研修指導医・藤沼康樹が語った。医学書院(=医学界新聞編集部)による公式リード文より
https://www.igaku-shoin.co.jp/paper/archive/old/old_article/n2003dir/n2544dir/n2544_01.htm